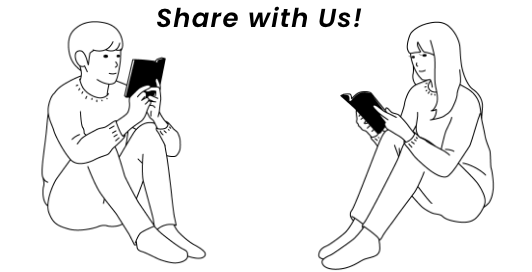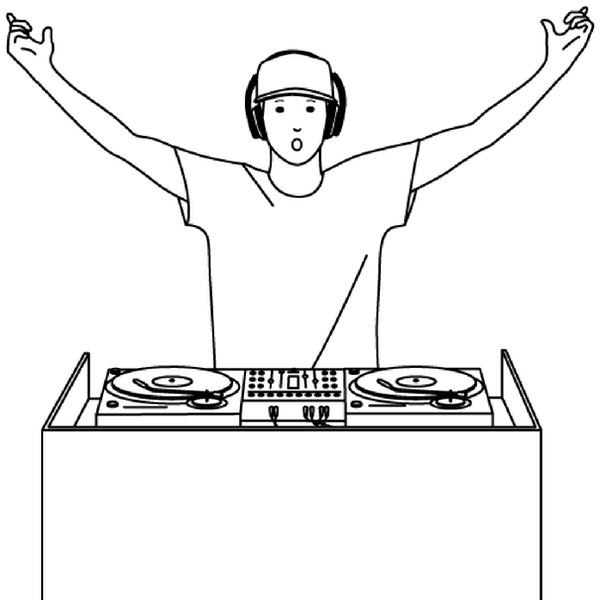日本食に寄り添うCAワイン カリフォルニアの 食に寄り添う日本酒
配信


プロフィール
中村 倫久(左) 迫 義弘(右)
中村 倫久(左) (なかむら・のりひさ)東京出身。叔父の経営するイタリアレストランでワインの魅力に触れる。1993年慶應義塾大学卒業、2002年にUC Davisでワイン醸造学科卒業。ナパやソノマでワインメーカーとして働き、2010年に自身のブランドNORIAを立ち上げた。 迫 義弘(右) (さこ・よしひろ)神奈川県出身。2000年に渡米し、音楽活動と並行してサンフランシスコにて日本酒とワインのバイヤー、ソムリエを経験。2017年、オークランドにてDen Sake Breweryを創業。酒造りを一手に担う。
この記事に関連する記事
-

2024.07.03 BMXが僕を強くしてくれる 世界選手権で表彰台を目指す
-

2025.04.30 エンジニア X 製麺屋 仕事も趣味も人生そのもの
-

2021.06.18 ビジネスとテクノロジーの橋渡しを-辻野宏幸
-

2024.10.02 今ではここが “ホーム” に 人生を築いたベイエリア
-

2021.06.18 【TOP VISION】iichiko USA.
-

2025.06.04 エネルギッシュな場所で 新しいことに挑戦する
-

2021.06.18 何事もまずは挑戦-安井のり子
-

2025.09.17 日本食に寄り添うCAワイン カリフォルニアの 食に寄り添う日本酒

一覧ページにもどる